小学校の音楽の教科書を見ると、
- 旋律の特徴を生かして歌いましょう
- 2拍子を感じて指揮をしてみよう
など、取り上げる曲で学習したい内容がページの上部に大きく示されています。
中高の教科書に比べて、先生にとっても授業する視点が最初から明確になっているのでわかりやすいですね。
 コギト
コギトただ、小学生にわかりやすく音楽を教えるのって結構難しいですよね。
小学生は理解できる言葉もまだ少ないため、とことん噛み砕いてわかりやすい言葉や具体物、図解などを使って授業していくことが必要になります。
教える内容は難しくないんだけど、どうやって教えるかという部分で難しいわけです。
今回は小学校ですぐに授業できるおすすめの教材を紹介しながら、小学校の音楽授業のネタやコツを紹介します!
 コギト
コギトカンタンに授業できる教材もたくさん紹介しているので是非最後までお読みください。
ブログ運営者

コギト|音楽教材研究家
- 音楽教員歴18年の元音楽教員
- 教員辞めても教材研究が好きで続けている
- 元作曲専攻で鑑賞や創作の授業が得意
- ピアノはコンクール全国大会入賞レベルでピアノ動画チャンネル(YouTube)も運営
- ICTを駆使・時短マニア
- noteで自作教材をアップ、3000ダウンロードを突破!
- 音楽や音楽教育に関することをX(Twitter)でも発信中

【歌唱授業のコツ】どのように歌えば良いかを明確に伝える

小学校の教科書の歌唱のページには次のように「ねらい」がページの上部に大きく載っています。
- 「ラバーズコンチェルト」→拍子の違いを感じ取り拍の流れにのって歌おう
- 「歌のにじ」→明るい声で歌いましょう
- 「風のメロディー」→6拍子を感じながら歌いましょう
- 「明日を信じて」→旋律の動きや強弱を生かしながら歌いましょう
 コギト
コギトなんでこの曲を歌うのか、という意味づけがしっかりしているからわかりやすいですね。
ただ、このまま子どもたちに示したとしても目標どおりに歌えるようにはなりません。
 生徒
生徒流れに乗って歌うって結局どうすればそうなるの?
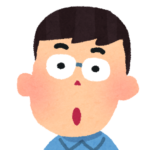 生徒
生徒拍子の違いっていうけど、拍子って何?リズムとは違うの??
 男子
男子明るい声で歌うって自分の声は変えられないけど…。声明るい人のモノマネすればいいの?
こんな風に子どもたちは疑問に思うかもしれませんね。
「明るい声で歌う」というねらいの場合を例に解説すると、生徒には例えば以下のようなことをわかりやすく理解させることが重要です。
- 明るい声とはどんな声のことを言うのか
- 明るい声で歌うにはどうすればいいのか
- 明るい声の使い分けができるようになったか
上のようなことを理解させるためには次のような具体的な指導を行います。
- 明るい声と暗い声2パターンの範唱をして、どちらが明るい声か聴きとらせる
- 明るい声で歌うために「口を大きく動かす・大きく開ける」「上を向いて歌う」などの具体的な方法を伝える
- 自分達の声を録音して聴いてみる
 コギト
コギト感覚的であいまいにならず、具体的な方法に落とし込んで指導することが大切ですね。
また歌唱のテクニックは説明しづらい、わかりにくいものが多いです。例えば以下のようなテクニックは小学生にはなかなか理解しにくいかもしれません。
- 軟口蓋を開けて響かせる
- 腹式呼吸で息を吸う
- 声を飛ばして歌う
これをそのまま指示されたところで子どもたちにとっては「え…どうやって?」と疑問に思われてしまいます。
歌唱に必要な発声テクニックも次のように具体的な行動として伝えることでできるようにしましょう。
- 軟口蓋を開ける→あくびをしている時の口の開け方だよ、口の中の上が持ち上がるでしょう?
- 腹式呼吸で→いい香りの花の匂いを嗅ぐように息を吸ってみよう、仰向けに寝て呼吸してみよう
- 声を飛ばす→音楽室の前の壁を突き抜けて隣の部屋まで届くように歌ってみよう
このように具体的なイメージで伝えていきます。
 コギト
コギト曲の指導目標をどのようにしたら実現できるのか、具体的な方法を考えて指導するのがコツです。
【鑑賞授業のコツ】曲や音の特徴を視覚的にもわかりやすく提示する
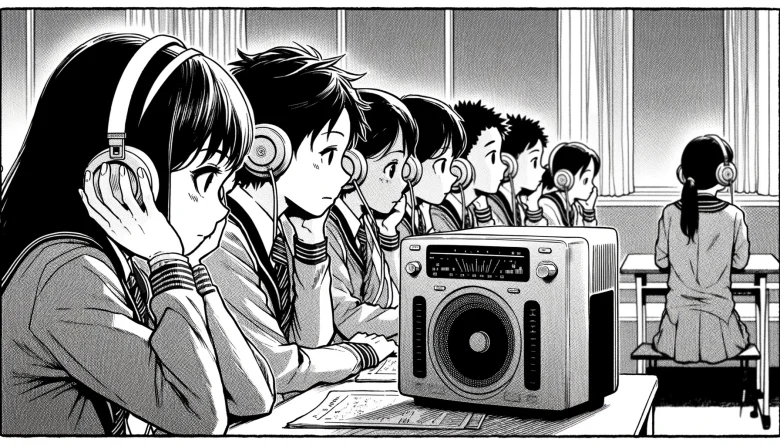
鑑賞のねらいを明確に
鑑賞曲の場合、教科書には「曲のおもしろいところをみつけよう」とか「変奏曲をたのしもう」のように割と大ざっぱな目標が示されています。
これだけですと、ただ鑑賞して感想や曲紹介をグループで発表させてあっさり終わりになってしまいがちです。
- 楽器の音色に注目させたいのか
- 強弱の変化に気をつけて聴かせたいのか
- 曲の表情が変わる部分に気づかせたいのか
このように教える側が、鑑賞する曲をよく理解して、どこを指導のポイントにするのかを決めておくことが大事です。
「ここはどんな音が聞こえた?」「こういうのは音楽で○○というんだよ」という風に授業の目標に向かって問いかけをし、持っていきたい方向に授業を誘導していきましょう。
かといって、音楽の鑑賞は本来自由なもの。「これが唯一の答えだ」という風な聴かせ方をするのも少し違う気がします。
↓鑑賞の授業のポイントに関する記事を参考にお読み下さい。
鑑賞の授業で先生がやってはいけない4つのことと、使えるフレーズ3選
 コギト
コギト完全に先生主導の授業でもよくないですが、生徒に丸投げもだめ。バランスが難しいですね。
子どもたちの自由な感じ方や発言は否定することなく汲み取りつつも、先生側で子どもたちに感じて欲しい点を問いかけしたり、解説したり、課題設定してみたり、という授業をコントロールする力が必要ですね。
図解や音源を示してわかりやすく
また、曲について説明するときに、言葉で音楽を説明しにくいのがそのまま音楽鑑賞の授業の難しいところになります。
このような場合には図解や音源などを使ってわかりやすくしましょう。
例えば、「ペールギュント」の「朝の気分」の鑑賞では「なぜこんな朝の爽やかな景色が浮かぶような音楽になるんだろう?」ということを説明するときに、以下のようなスライドで説明すると面白いです(ツイートの動画を再生してみてください)。
- 図や写真、音源、動画を挿入できて生徒にわかりやすい説明になる
- スライド自体が授業の台本になり、授業しやすい
 コギト
コギトスライドで説明するとスライド自体が授業の台本になるから、授業が迷子にならないので経験の浅い先生にもおすすめ。
このように音源・図解・動画付きで作り込んだスライドを使うと鑑賞授業が一気に楽になります。
 新米先生
新米先生でもそんなスライドを作るのって大変…
以下のnoteでスライドデータがダウンロードできちゃいますので是非使ってください。(有料です)
また鑑賞の授業では生徒に感想などを書かせる場合、「曲を聴いて感じたことは確かにあるけれど、それをどんな言葉で表現していいのかわからない」といったこともあるあるです。
そんな時には「音楽を表現することば」の一覧を示して、それを参考にワークシートを書かせるとスムーズにいきますので試してみてください。
\無料でダウンロード!/
「音楽をあらわすことば」のプリントを無料ダウンロード
【創作授業のコツ】とにかくスモールステップで進める

創作の授業はうまくやるのがとても難しい授業として音楽の先生の頭を悩ませてきたのではないでしょうか。
- 創作するために和音や音階などの予備知識が必要
- 創作するには楽譜を書いて記録させなければいけない
- 創作したものを演奏する技術も必要
このように創作をさせるには、演奏もソルフェージュも、いろいろな知識や技術が必要になるから大変だったのです。
 コギト
コギトそれを小学生にやらせようと思うと結構至難の技…
しかし今はGarageBandやChrome music LabなどのICT機器のアプリにより、音楽の創作が初心者にも簡単にできるほどになり、ハードルが大きく下がりました。
- 和音や音階はアプリで簡単に設定できる
- 創作したものを保存できるので楽譜を書く必要がない
- 創作したものを自動演奏してくれる
このように、音楽製作アプリで創作すれば、創作だけにフォーカスして教えることができるようになるので、今の時代の創作授業には音楽アプリはマストなツールと言えます。
小学校の創作の授業は低学年でリズム創作を経過して、高学年では簡単な旋律の創作に進みます。
リズムを創作する場合には、Chrome music Labの「リズム」アプリや「ソングメーカー」アプリが無料で活用できます。
Chrome music Labの使い方についてはこちらの動画で紹介しています。
Chrome music Labの14のアプリを全て解説した記事もありますので参考にしてください↓
【すぐわかる!】クロームミュージックラボとは?使い方と音楽授業での活用方法を完全解説!
自分の学校の「校歌にドラムをつけよう!」という単元も記事にしているので参考にしてください。(iPadのアプリである「GarageBand」を使用します)
iPadで音楽授業「校歌にドラムをつけよう」① 【GarageBandで創作】〜準備編
iPadで音楽授業「校歌にドラムをつけよう」② 【GarageBandで創作】〜授業編
旋律の創作については、以下の教材が便利ですよ。
【お試し版!】音楽づくり授業ネタ(短い旋律づくり)〜作曲をしてみよう!〜
【小学4、5年生】5音音階でたのしい「せんりつづくり」教材セット
【小学校5・6年】全員作れる!和音の音で旋律づくり
【器楽授業のコツ】常時活動で定着を目指す

小学校で行う器楽といえば、以下が挙げられます。
- リコーダー
- 鍵盤ハーモニカ
- 和楽器(和太鼓など)
- 合奏
 コギト
コギト一番よく使うのはリコーダーや鍵盤ハーモニカだと思います。
鍵盤ハーモニカ
鍵盤ハーモニカは一人一台の鍵盤楽器として、電源もいらず、とても取り回しのいい楽器です。
 コギト
コギト私は演奏よりも、音楽の学習として使うことが多いです。
- 歌唱曲に出てくる旋律を弾いてみてメロディラインを確認させてみたり
- 鑑賞曲のメロディや和音を弾いてみたり
- 音階や和音の学習に使ったり
このように使うと、歌唱や鑑賞、音楽理論の学習の合間に演奏を取り入れてリズムのある授業を展開できますし、歌唱と器楽、鑑賞と器楽を同時に学習することができて一石二鳥。
 コギト
コギトこのような使い方ができるから、中学校でも鍵盤ハーモニカ使うと良いんじゃないかな、と思っているくらいです。
リコーダー
基本的に単音しか出ないリコーダーは鍵盤ハーモニカのように便利に使うことはできません。
しかし吹奏楽やオーケストラの世界に入ることがなければ、生涯で経験する「管楽器」といえばリコーダーだけ、という人がほとんどではないでしょうか?
そのような意味で、リコーダーを学習するのはとても意味があることだと思います。
 コギト
コギトリコーダーに触れて上達していくためには「常にさわること」が大事です。
先生たち大人にしても、楽器を上達するなら、
「1ヶ月に一度だけ5時間練習する」より「1日10分毎日練習する」方が上達が早いと思います。
このように考えると、リコーダーを演奏する月を設けるのではなく、常時活動として「毎回音楽の授業のはじめの10分はリコーダーの練習をする」と決めておくと上達がはやくなりますし、授業もパターン化できて先生が楽になります。
↓常時活動の取り入れ方については以下の記事も参考にしてください。
【音楽授業のコツ】常時活動をつくれば楽しい授業ができる!
↓ソプラノリコーダーの授業用の便利教材あります。

【楽典授業のコツ】高い・低い・大きい・小さいをないまぜにする子どもたち
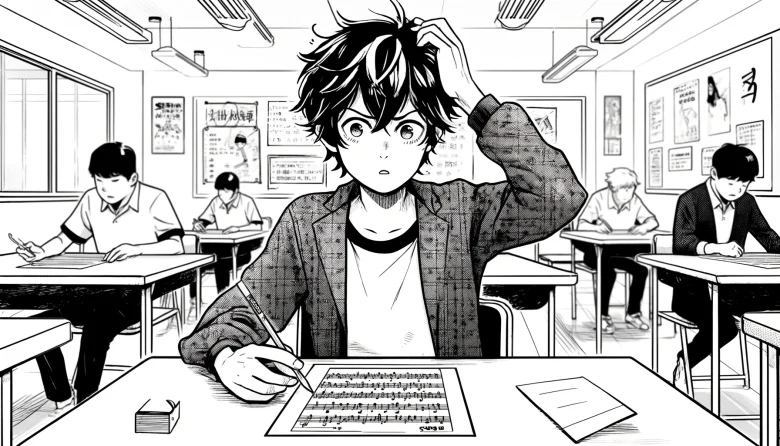
歌唱の部分で、「わかりやすく、簡単な言葉でイメージさせること」の重要さを書きましたが、それとは別に音楽の知識や音楽用語を覚えていくことは大事です。
われわれが当たり前のように使う「音が高い・低い・強い・弱い・大きい・小さい」などの言葉ですが、一般常識といわれるレベルの音楽用語でも子どもたちは誤って認識していることも多いです。
- 高い音を「大きい音」と表現する
- 弱い音を「高い音」と表現する
こんな誤解はよくみられます。支援を要する子どもの場合は特に多いです。
このような誤解をしたままだと、授業でいくら先生が曲の説明をしたとしてもまったく違う意味で理解されてしまいかねません。
 コギト
コギト初歩的な言葉の意味をしっかり理解させていくことが大事です。
【「おと」の学習教材】
— コギト🎸音楽の授業研究家 (@COGITOmusic) April 3, 2024
音の大小と高低をごっちゃにする児童や生徒は以外と多いです。
さらに「強い」「弱い」という表現も入ってきてさらに混乱というパターンも😅
図解やイラストでわかりやすく説明しています。 pic.twitter.com/sE60D2s7HT
上のスライドが使える、小学校の楽典は以下の教材で学習できます。
【小学校・中学校・特別支援】「おと」の学習音楽授業ネタ(音楽鑑賞の準備に)
「高い・低い・大きい・小さい」の違いから「音階」と「メロディ」の違い、和音や調などをわかりやすく、音付きのスライドとワークシートで学習することができます。
また、小学校で学ぶ音楽用語の総復習プリントもありますので、自習などで使えます!
リズムの学習は分数の要素が入ってきてとても難しいです。原理を教えても頭がごちゃごちゃになるので、コツはとにかくリズムを読みまくること。
リズム学習のダウンロード教材「リズムフラッシュカード50問」はゲーム感覚・レベル上げ感覚でリズムを学習できる優秀ツールです。
【リズム学習決定版!】フラッシュカード50問&カード作成ツール
小学校の音楽の授業はひとつひとつ丁寧に!

小学校の音楽授業のコツをまとめると以下のようになります。
- 教材研究はしっかりして、曲のポイントや自分なりの伝えたい点を掘り下げておく
- なるべくわかりやすい言葉や例示、図にして伝える
- ICT機器を利点をいかす(特に創作授業)
- 定着が必要な課題(リコーダー技術など)は常時活動化する
- 音楽用語など知識を少しずつつけていく
あなたが実践しているその他の授業のコツがありましたら、是非コメントやツイッターで教えてください。とっても参考になります!
音楽自体がとても自由なものであるがゆえに、音楽の授業もどの視点からどんな授業にするのかという選択肢は大きく広がっています。
 コギト
コギト他の教科と合わせたような単元も面白いですよ。
【鑑賞・創作・図工!】パパパの二重唱を使った大きな単元の教材
教員歴18年の私が作成した小学校音楽用の授業ネタはこちらからダウンロードできます↓
どの教材も研究授業でも耐えられる充実した内容。10時間以上かけて作った超使える・授業準備が1/3になる便利な教材なので是非チェックしてみてください。

無料教材もある!
今回は以上です!












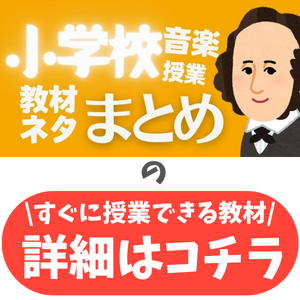

コメント