 新米先生
新米先生常時活動って大事ってよくいうけどどんな感じでやればいいのかしら…
この記事は音楽授業の常時活動について解説する記事です。
常時活動とは、毎回授業で行う活動のこと。
 コギト
コギト授業の最初によくやる「発声練習」なども この常時活動ですね。
このいわゆる定番ネタが常時活動で、常時活動を作っておくメリットは以下があります。
- 短い活動なので飽きない・長い期間かけて習得できる
- 授業にリズムや緩急を作ることができる
- 生徒も先生も毎回のお決まりで安心できる
- 授業の時間調整に使える
常時活動あると授業に安定感出ますよね。
例えば鑑賞でメインの授業を予定していたのに、オーディオの不具合で鑑賞ができなくなったとかいった場合、もしその他の活動の準備が何もなければ、その場で呆然と立ち尽くすしかなくなり、パニックです…(経験あり)。
 新米先生
新米先生授業中にフリーズするのとか怖っ…
でも、こんなときに「普段常時活動として歌っている曲」とかがあれば、歌に活動を切り替えてその場をしのぐことができますね。
 コギト
コギト授業に保険をかけておくイメージですね。
また、小学校では特に一つの内容を45分や50分の授業でずっとやっているとほぼ飽きられます(よっぽど授業力がある先生なら別かも)。
メインの授業内容だけで一コマの授業時間を埋めるのではなく、常時活動のような活動も織り交ぜて2つ〜3つの活動をテンポよくポンポンと進めていくと、小学生でも飽きずに授業に参加することができます。
 コギト
コギト子供向け番組とかもそういう構成で進めていますもんね。飽きそうになったら次にいく。
経験の少ない先生や音楽の専門外の先生は特にこの「常時活動」を作るところから授業をスタートさせることをおすすめします。
鑑賞の常時活動に:「動物の曲」鑑賞13曲スライド、ワークシート付き
リズム学習の常時活動に:「リズムフラッシュカード50問」
記事では常時活動の例も紹介していますので是非最後までお読み下さい!
ブログ運営者

コギト|音楽教材研究家
- 音楽教員歴18年の元音楽教員
- 教員辞めても教材研究が好きで続けている
- 元作曲専攻で鑑賞や創作の授業が得意
- ピアノはコンクール全国大会入賞レベルでピアノ動画チャンネル(YouTube)も運営
- ICTを駆使・時短マニア
- noteで自作教材をアップ、3000ダウンロードを突破!
- 音楽や音楽教育に関することをX(Twitter)でも発信中

常時活動のメリットを知ってうまく使いこなそう!
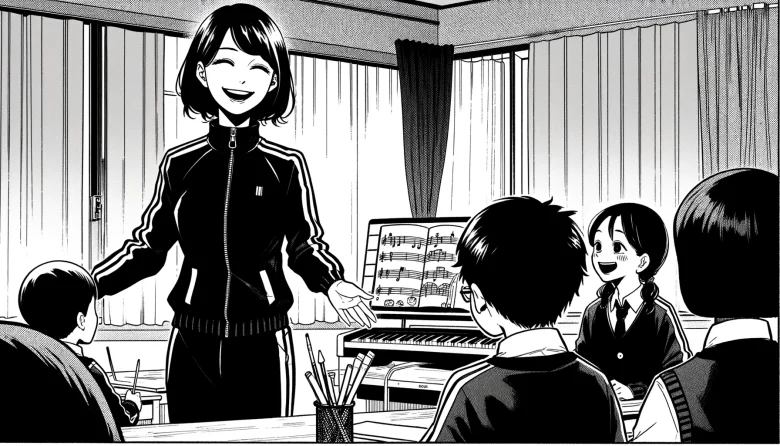
毎回行う定番の活動である常時活動のメリットは先程確認した通り以下です。
- 短い活動なので飽きない・長い期間かけて習得できる
- 授業にリズムや緩急を作ることができる
- 生徒も先生も毎回のお決まりで安心できる
- 授業の時間調整に使える
 コギト
コギト一つずつ解説します。
①短い活動で飽きない・長い期間かけて習得できる
常時活動はメインの活動とは違い、授業の最初や途中、終わりなどに短い時間で設定することになります。
お決まりといえば発声練習ですね。
発声の指導は1時間みっちりではなく常時活動で行うのが適しています。理由は以下です。
- 地味で飽きやすいし疲れやすい
- 一度や二度の授業では習得できない
長期間にわたって継続的に行わないと定着しにくい学習内容は常時活動に向いています。
 コギト
コギト常時活動は「短時間で長期間」が合言葉。
- 発声練習
- リコーダーや鍵盤ハーモニカの練習など
- 楽譜についての学習
詰め込まにならず少しずつ学習していけるのがいいところ。
②授業にリズムや緩急を作ることができる
常時活動で授業にリズムや緩急をつけることができます。
たとえば以下が例です。
- 鑑賞がメインの授業の時は座っている時間が長いので、常時活動ではボディパーカッションをする
- 歌や器楽がメインなので、常時活動では活動量の少ない鑑賞を行う
 新米先生
新米先生なるほど、「静↔動」と変化させるのね…。
- 歌う活動から聴く活動へ
- 立って行う活動から座って行う活動へ
- 一人で考える活動からグループで話し合う活動へ
このように1時間の授業の中で内容だけでなく、聴くのか歌うのか、考えるのか表現するのか、書くのか話すのか、という具合に活動を変化させていくことでメリハリのきいた授業にすることができます。
 コギト
コギト常時活動を取り入れると実現しやすくなりますね。
③子供も先生も毎回のお決まりが安心
「ルーティン」という言葉があるように、私たちはお決まりのパターンがあると安心します。
 新米先生
新米先生音楽にだってお決まりの流れがあるものね…
 コギト
コギト特別な支援が必要な生徒(支援級の生徒)が授業を受けている場合は特に常時活動で作られたお決まりのパターンが効果的。
支援級の生徒には毎回のパターンが決まっていた方が安定して授業が受けられる生徒が多いですし、理解や成長がゆっくりな彼らも、毎回の常時活動で地道に続けていけばできるようになることもたくさんあります。
ルーティンで安心するのは先生もしかりです。
毎回の授業が全て新しい内容、ぶっつけ本番、一本勝負だと、授業は成功するか失敗するかの「ばくち」のようになってしまい、安心して授業が進められません。
 新米先生
新米先生とりあえずこれやっとけば、っていう毎回のものがあるのは確かに安心だね。
④授業の時間調整に使える
常時活動の時間設定を変えることで授業全体の時間調整ができるのも大きなメリットです。
 新米先生
新米先生やばい、時間が余る!
となってしまった場合は「じゃあ、最初に歌った今月の歌をもう一回歌って終わりにしよう。」と常時活動を持ってくることができます。
 新米先生
新米先生今日はメインの活動時間かかりそうだな…、終わるのか?
と心配な授業では、常時活動を短く設定したり、「今日はなしね。でも時間が余ったら後でやるよ。」としておくと時間調整も可能になります。
音楽の授業でおすすめの常時活動

常時活動として以下の活動などが一般的なのかな、と思います。
- 発声練習
- テーマに沿った曲の鑑賞
- 音楽の理論の学習
- 月や学期で決めた曲の歌唱・演奏
 コギト
コギト以下にコギトおすすめの常時活動を紹介します。
常時活動例①:4月は「とりあえずこれ歌おう!」
4月にはまず授業を走り出させることが大事。何はともあれ簡単な常時活動を設定してしまいましょう。
 先輩先生
先輩先生一回やってみてダメなら次の授業からすぐ変えてもOK。いろいろ試してみるといいわよね。
4月は生徒が緊張していると思うので、生徒が好きそうで簡単に歌えてノレる曲をチョイスして歌ってみるのがおすすめの常時活動です。爽やかで声が出しやすい(歌いやすい)曲をチョイスしましょう。
良い感触がつかめたら、「今月の歌」などを決めていろんな曲を歌っていくのは定番の常時活動です。
 コギト
コギトジブリの曲はよくお世話になりました。
- 歌の選曲はどうやってするの?
-
*曲の選定について私の基本的な考え方は、「自分の美意識に従う」です。曲の選択を生徒の好みや今の流行りに無理に合わせる必要はそんなにないと私は考えています。流行りの曲じゃなくても以外と生徒はのってくれるものですし、いつも聴かないような曲を演奏する方が経験にもなります。昔「小雨降る径」という短調の昭和激シブなシャンソンを歌ったこともあります(生徒ちゃんと歌ってました)
常時活動例②:リズム学習
リズムや楽譜などの音楽の理論的な側面は理解するのに時間がかかります。常時活動として設定し、「短時間で長期間」学んでいくようにするのも一案です。
特にリズムの学習を理論として理解するには分数の要素が入ってくるため、どうしても学習が難しくなります。
 コギト
コギト進学校の高校でバンド組んでいたことがありますが、リズムを楽譜から読むというのはなかなか難しい友達もいました。小学生ならなおさら。
私が小学校でリズムを教える際気をつけている点は、リズムは理屈で教えるのではなく、九九を覚えるように体に染み込ませて覚えていく、ということです。
 先輩先生
先輩先生楽譜読める人はいろんなリズムパターンを暗記しているから、いちいち考えなくてもリズムがすぐ頭で鳴るのよね。
誤解を恐れずにいえば、暗記教科的な「詰め込み」で教えちゃってよいわけです。
リズムを体に染み込ませるために、フラッシュカードがよく使われます。
↓簡単にリズム学習を常時活動にできる教材がありますので是非使ってみてくださいね。
【決定版】「リズムフラッシュカード50問」

常時活動例③:「テーマに沿った曲の鑑賞」
音楽の授業の常時活動として「鑑賞」もよく行われます。
10分程度の時間で毎回1曲何かしらの曲を鑑賞していきますが、常時活動では「ただ聴かせておわり」になりがちなので注意が必要です。
聴かせるだけ鑑賞授業は研究授業で怒られるやつ。
「生徒○○さんのおすすめの曲」とか、「季節に合う曲」「教科書に載っている曲」を選んでただ鑑賞するだけというのでなく以下のような工夫をすると充実した常時活動にすることができます。
- 桜の曲を4月で何曲か聴いて、それぞれ桜のどんなところを表現しようとしているか比較する
- 生徒おすすめの曲を鑑賞する場合は、紹介者に曲のどんな部分がおすすめなのか音楽的に解説させる
- 名曲をカバーしたいろいろな曲を聴いてみて、楽器編成や編曲の特徴を比較
- さまざまな土地の音楽を聴いて、音楽や使われている楽器とその土地の文化を考えてみる
 コギト
コギト「音楽をある一つの視点から捉えてみる」という切り口があると音楽の授業としての意義がしっかりしてきます。
 教員
教員おすすめの鑑賞ネタはある?
「動物の曲の鑑賞」という動物の曲を13曲集めた単元は常時活動にもおすすめ。
「ライオンの行進(サン=サーンス)」を聴いて、ライオンの怖さや大きさが音の大きさや低さで表現されているなど、「この音楽のどこが動物を表現しているのか」を考えていく題材。
まとめ 常時活動をうまく活用して余裕ある授業展開を!

 コギト
コギト常時活動を入れて飽きさせない、テンポの良い授業を作っていきましょう!
- 生徒への活動量の調整
- 授業時間の調整
- 先生の準備など負担の調整
常時活動を使って緩急をつけながら授業を組み立てられると1年がスムーズに回せるようになります。上手に取り入れてみてくださいね。
↓「楽しい音楽の授業ができるコツ」という記事も書いているので是非読んでみてください。

今回は以上です!









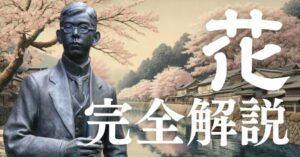


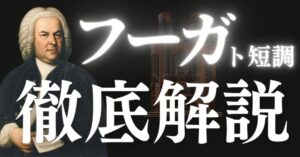
コメント