クラシックには「動物」を表現した曲がたくさんあります。
聴いてみるとさすがにクラシックと言われるだけのことはあり、100年以上も絶えずに聴かれてきた曲なので「なるほど〜」とうなってしまうような表現力の曲ばかり。
この記事では「動物を表現したクラシック曲」を18曲、動画つきで紹介します。
 コギト
コギト気になる曲があれば下の目次からジャンプして聴くことができますので、聴いてみてください!
↓「動物の曲鑑賞」の音楽授業ネタもダウンロードできます↓
では一つずつ解説していきます!
ブログ運営者

コギト|音楽教材研究家
- 音楽教員歴18年の元音楽教員
- 教員辞めても教材研究が好きで続けている
- 元作曲専攻で鑑賞や創作の授業が得意
- ピアノはコンクール全国大会入賞レベルでピアノ動画チャンネル(YouTube)も運営
- ICTを駆使・時短マニア
- noteで自作教材をアップ、3000ダウンロードを突破!
- 音楽や音楽教育に関することをX(Twitter)でも発信中

動物を表すクラシックの曲18選
 コギト
コギト曲の一覧は以下です!
- 「ライオンの行進」/サン=サーンス
- 「雌鳥と雄鶏」/サン=サーンス
- 「騾馬」/サン=サーンス
- 「亀」/サン=サーンス
- 「象」/サン=サーンス
- 「カンガルー」/サン=サーンス
- 「水族館」/サン=サーンス
- 「森の奥のカッコウ」/サン=サーンス
- 「白鳥」/サン=サーンス
- 「蝶々(ちょうちょう)」/グリーグ
- 「ハエの日記から」/バルトーク
- 「クマンバチの飛行」/リムスキー=コルサコフ
- 「ギャロップ」/カバレフスキー
- 「ワルツィング・キャット」/アンダーソン
- 「金色の魚」/ドビュッシー
- 「牛車(ヴィドロ)」/ムソルグスキー
- 「卵の殻をかぶったひな鳥のバレエ」/ムソルグスキー
- 「ウタツグミ」(鳥の小スケッチ)/メシアン
一曲ずつ見ていきましょう!
1:「ライオンの行進」/サン=サーンス
組曲「動物の謝肉祭」より「ライオンの行進」/ サン=サーンス作曲
Le carnaval des animaux , Marche royale du lion / Charles Camille Saint-Saëns
「ライオンの行進」は編曲されてピアノ初心者のための曲にもなっているため知っている人も多く有名です。
低い音や大きな音、短調(正確にはドリア旋法)で百獣の王ライオンを表現しています。
 コギト
コギトピアノで演奏される、半音階のパッセージはライオンの吠える声を表現しているようです。
2:「雌鳥と雄鶏」/サン=サーンス
組曲「動物の謝肉祭」より「雌鳥と雄鶏」/ サン=サーンス作曲
Le carnaval des animaux , Poules et coqs / Charles Camille Saint-Saëns
- ピアノとヴァイオリンが雄鶏を(同音連打が特徴のパッセージ)
- ピアノとクラリネットが雌鳥を(前打音とトリルが特徴のパッセージ)
それぞれ表現しています。
それぞれの鳴き声を音で表しているようですね。
3:「騾馬」/サン=サーンス
組曲「動物の謝肉祭」より「騾馬」/ サン=サーンス作曲
Le carnaval des animaux , Hémiones / Charles Camille Saint-Saëns
急速なピアノのパッセージだけで表される「騾馬」。
 コギト
コギト騾馬とは雄のロバと雌の馬の交雑種のことで主に家畜として用いられました。
副題として「Animaux Véloces」(敏捷な動物)と書かれていて、プレスト(急速な)音楽に仕上がっています。
4:「亀」/サン=サーンス
組曲「動物の謝肉祭」より「亀」/ サン=サーンス作曲
Le carnaval des animaux , Tortues / Charles Camille Saint-Saëns
メロディを聴いてみると、この「亀」という曲に使われているメロディは有名なオッフェンバックの「天国と地獄」↓なんですよね。
運動会の徒競走のBGMにも使われる「速い・急ぐ」代名詞のこの曲のテンポをスローにしてゆっくりな「亀」の曲として使うというのはサン=サーンスのユーモアが感じられて茶目っ気たっぷりですね。
5:「象」/サン=サーンス
組曲「動物の謝肉祭」より「象」/ サン=サーンス作曲
Le carnaval des animaux , L’éléphant/ Charles Camille Saint-Saëns
ピアノ低音の3拍子の伴奏に、コントラバスのおっとりとしたメロディがつくなんとも平和な音楽です。
 コギト
コギトコントラバスの鼻にかかったくぐもった音色が象のイメージとマッチしていますね。
6:「カンガルー」/サン=サーンス
組曲「動物の謝肉祭」より「カンガルー」/ サン=サーンス作曲
Le carnaval des animaux , Kangourous / Charles Camille Saint-Saëns
不規則なリズムがカンガルーのぴょんぴょん跳ねる様子を表しているように聴こえる曲。
不規則なリズムの後の長くのばす和音は、カンガルーが止まっているところか、と聴きとることができます。カンガルーってフリーズするみたいに止まったりしますもんね。
↓カンガルーの動き
7 :「水族館」/サン=サーンス
組曲「動物の謝肉祭」より「水族館」/ サン=サーンス作曲
Le carnaval des animaux , Aquarium / Charles Camille Saint-Saëns
半音進行を利用した和音や高い弦楽器の音で神秘的な雰囲気が醸し出され、海の底にいるような深くて暗い感覚を受けます。
 コギト
コギト和音と音色の使い方に力点が置かれた作品ですね。
8:「森の奥のカッコウ」/サン=サーンス
組曲「動物の謝肉祭」より「森のおくのカッコウ」/ サン=サーンス作曲
Le carnaval des animaux , Le coucou au fond des bois / Charles Camille Saint-Saëns
ピアノで和音の伴奏が奏され、合いの手のようにクラリネットの「カッコー」という旋律が演奏されます。
 コギト
コギトピアノ伴奏は森の奥の静けさを表現しているよう。
クラリネットの部分の楽譜には「dans la coulisse(舞台裏で)」と書かれていて、遠くからカッコウの声が聴こえてくるような音響効果を出しています。
9:「白鳥」/サン=サーンス
組曲「動物の謝肉祭」より「白鳥」/ サン=サーンス作曲
Le carnaval des animaux , Le cygne / Charles Camille Saint-Saëns
言わずと知れた名曲でクラシックの初心者でもどこかで必ず聴いたことがあるでしょう。
ピアノの伴奏はゆらゆら揺れる水面を表すようで、その上にチェロの優雅な旋律が乗ります。
10:「蝶々(ちょうちょう)」/グリーグ
「抒情小曲集」より「蝶々」/ グリーグ作曲
Lyriske smastykker No.3 , Sommerfugl / Edvard Hagerup Grieg
グリーグのピアノ曲集「抒情小曲集」の中の一曲。
付点のリズムが蝶の不規則な動き、パタパタする音型が蝶の羽根の動きを表しているよう。
 コギト
コギト蝶のはかなさが、不安定な和音の使い方で絶妙に表現されていますね。
11:「ハエの日記から」/バルトーク
ピアノ練習曲集「ミクロコスモス」より「ハエの日記から」/ バルトーク作曲
Mikrokozmosz ,From the Diary of a Fly / Béla Bartók
狭い音域で行ったり来たりする半音階が身の回りを「ぷぅ〜ーうーーん」と飛び回るハエの鬱陶しさを本当に上手に表現しています。
中間部には「うわ!蜘蛛の巣だ!」と楽譜に書かれたピンチの場面もあって面白いです。
 コギト
コギト最後は机の上かどこかに「ぴたっ」と止まる感じで曲が終わるんでそこもおもしろいです。
12:「クマンバチの飛行」/リムスキー=コルサコフ
オペラ「サルタン皇帝」より間奏曲「くまんばちの飛行」/ リムスキー=コルサコフ作曲
Flight of the Bumblebee / Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov
急速な半音階のパッセージと短調の和音がくまんばちの「危険」さを表現しています。
2音のトレモロのようなパッセージはブンブン唸るクマンバチの羽音に似せていますね。
13:「ギャロップ」/カバレフスキー
組曲「道化師」より「ギャロップ」/ カバレフスキー作曲
Suite: “The Comedians” , Gallop / Dmitri Kabalevsky
運動会でお馴染みのこの曲。ギャロップとは馬術で「1番速い走り方」を表す用語で、音楽的には舞曲の形式のことも指しますが、この曲の場合には前者の意味でしょう。
14 :「ワルツィング・キャット」/アンダーソン
「ワルツィング・キャット」/ アンダーソン作曲
The Waltzing Cat / Leroy Anderson
優雅なワルツの曲に合わせて弦楽器のポルタメント奏法による「ニャーオ」という鳴き声を模したフレーズがはさまります。
 コギト
コギト三部形式で中間部はテンポが少しはやくなり、猫が自由に駆け回る様子が描写されているようです。
最後には犬の鳴き声が加わって、猫が逃げ出す?というオチがついているキュートでコミカルな1曲。
15 :「金色の魚」/ドビュッシー
「映像第2集」より「金色の魚」/ ドビュッシー作曲
Images II , Poissons d’or / Claude Achille Debussy
くぐもった和音の連続(水底を眺めているのでしょうか)から始まるこの曲。次第にキラキラと太陽に反射する水面や、光る魚の鱗がピアノで表され、目に見えるようです。
ちなみにドビュッシーはジャポニスムに傾倒してこの曲を書いていますが、「金色の魚」は「金魚」のことではなく、ドビュッシーが持っていた日本の漆器盆に金粉を用いて描かれていた錦鯉に触発されたとか。確かに金魚がイメージだとこんなにダイナミックな曲にはならないですね。
16 :「牛車(ヴィドロ)」/ムソルグスキー
組曲「展覧会の絵」より「ヴィドロ(牛車)」/ ムソルグスキー作曲
Pictures at an Exhibition , Bydlo / Modest Petrovich Mussorgsky
低音の管楽器であるチューバのソロで荷物を載せて重々しく動く牛車が表現されています。
 コギト
コギトピアニッシモから始まりだんだん大きくなってくるこの曲は牛車が遠くからだんだん近づいてくるような視覚的な効果もねらっています。
近づいてきて大迫力の音楽になるこの曲は「牛車」の表現にしてはオーバーであるように聴こえます。実はポーランド語である「Bydlo(ヴィドロ)」は「牛車」の意味のとは別に「家畜のように虐げられた人々」という意味合いも含んでいるとのこと。
当時圧政に苦しんでいたポーランドにロシアのムソルグスキーがどのように感じ、この曲を書いたのか一考に値するのではないでしょうか。
17:「卵の殻をかぶったひな鳥のバレエ」/ムソルグスキー
組曲「展覧会の絵」より「卵の殻を被った雛鳥の踊り(牛車)」/ ムソルグスキー作曲
Pictures at an Exhibition , Ballet des poussins dans leurs coques / Modest Petrovich Mussorgsky
同じくムソルグスキーの「展覧会の絵」の中の一曲です。高い音と速いテンポでちょこちょこと歩く雛鳥が音で表現されている可愛い曲。
18:「ウタツグミ」(鳥の小スケッチ)/メシアン
「鳥の小スケッチ」より「ウタツグミ」/ メシアン作曲
Petites Esquisses d’oiseaux , La grive musicienne / Olivier-Eugène-Prosper-Charles Messiaen
 コギト
コギト鳥類学者でもある作曲家のメシアン。世界中の鳥の鳴き声を採譜したことで有名。
鳥の曲として最も有名なのは「鳥のカタログ」という曲集ですが、この曲は「鳥の小スケッチ」という曲集の中の1曲で、ウタツグミの実際の鳴き声と比べてみればわかりますが、かなり詳細に鳥の声を再現していることがわかります。
↓ウタツグミの鳴き声
動物を表現したクラシック曲はわかりやすい名曲がたくさん

動物の曲を表現したクラシック曲は、雰囲気に止まらず、音の個性を十分に駆使して動物を表現している曲がたくさんあり、その工夫や表現力にただただ圧倒されるばかり。
「交響曲○番」のように抽象的な曲でなく、動物がモチーフになっているので、子供に聴かせてもイメージが湧きやすく、親しみやすいのも良いところ。音楽に興味を持つきっかけとしては最適ですよ。
ぜひ聴いてみてください!
 コギト
コギト動物の曲が13曲セットになった授業用教材がダウンロードできます!
音楽の授業準備が大変とお困りの先生へ
教材準備の時間を3分の1にして定時退勤しながらも生徒が前のめりになるおもしろい授業をする方法
わかりやすく簡単に「動物の曲」の鑑賞・創作・器楽授業ができるダウンロード教材あります!
- わかりやすい図解・音源入りのスライドデータ
- ワークシートもついてすぐに授業ができる!
授業のネタがこれでもかと詰め込まれ、この教材だけで授業できるセットになっています。
以下のリンクから教員歴18年のベテラン音楽教員が10時間以上をかけて作り込んだ授業用教材が1クリックで手に入ります。
動物を表現した曲は表現内容そのものに愛着が持てるため、鑑賞しやすくどれも程よく短めの曲が多いです。小学校から高校まで幅広く鑑賞授業として取り上げられる題材です。
小学校では「動物あてクイズ」、高校では表現を深掘りしたグループワークなど多彩に展開することができます。またライトに常時活動として毎回の音楽の始めに1曲ずつ鑑賞するのもあり。
とても使い勝手の良い教材になっていて私自身もこれが十八番の授業の題材にしていました。
この教材は有料ですが、無料でネットに落ちている指導案やワークシートとはまったく別物。超作り込んだ教材です。教材は随時アップデートも行っているので、教科書が変わって古くなってしまうこともありません。スライド・ワークシート全て揃っているオールインワンの教材は他にはありませんよ。
↓気になった方は教材をチェックです!

準備短縮しておもしろ授業
今回は以上です!



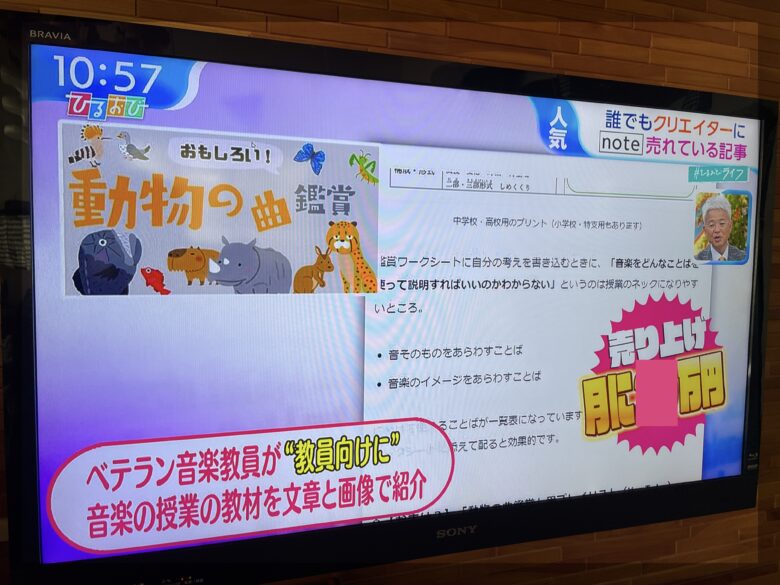





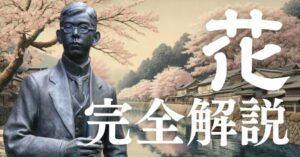


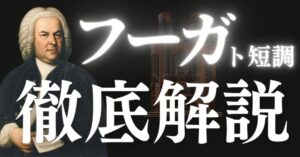
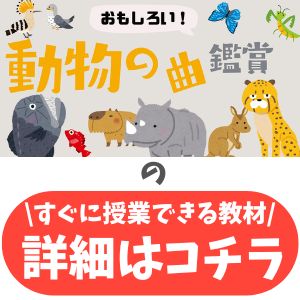

コメント