今日は教材づくりや授業をやっていて感じる「創作の授業の際に気をつけること」を3つ紹介します。
以前のツイートです。
これについて一つずつ解説していきます。
 コギト
コギト大学の時は作曲を専攻していたので、作っている側からいろいろ言えることがあります。
↓コギトが作成した創作授業用の教材各種あります

コギト | 音楽教材研究家
- 音楽教員歴18年の元音楽教員。辞めても教材研究が好きで続ける
- 元作曲専攻で鑑賞や創作の授業が得意、ICT・時短マニア
- ピアノはコンクール全国大会入賞レベルでピアノ動画チャンネル(YouTube)も運営
- ICTを駆使・時短マニアnoteで自作教材をアップ、3000ダウンロードを突破!
- 音楽教員のためのオンラインサークル「ムジクラブ」運営中
創作(旋律づくり)の音楽授業のコツ3選

- 曲例をたくさん聴く・弾く
- 時間をたっぷりとる
- 範囲を絞って創作させる
これらが大事です。ひとつずつ解説します。
① 創作の参考となる曲をたくさん聴く・弾く
創作を行う時、作ろうとする曲に似た曲の例をたくさん聴かせておきます。
 生徒
生徒創作ってどんな感じのを作ればいいのかわかんない!
と、子どもたちは最初創作のイメージがつかめないのはよくあること。
「こういう感じのものをつくるんだよ」と見本を見せることが大事よね。
見本となる曲を数曲挙げ楽譜もつけたりして、聴いたり・弾いたりすることができるようにしています。
創作は、頭の中から音楽を生み出すことですが、誤解を恐れずに言えば、「今まで聴いたことのある音楽からしか生み出されない」ものとも言えます。
創作と言われると何か全く新しいものを生み出さねばというイメージがありますが、実際それができるのは一部の天才のみといえます。
ほとんどの作曲家や作曲する人は全てそれまでの音楽経験を参考にしながらそこに少しずつ付け加える形で自分の音楽を作っていきます。
新しく12音音楽を始めたシェーンベルクでさえ、それまでの調性音楽を深く知り尽くした上で12音音楽にたどり着けた、ということができるでしょう。
 新米先生
新米先生ジャズの即興だって、練習したフレーズの引き出しから演奏するわけだしね…
小学生の創作に話を戻すと、小・中学生は「今までの音楽経験」がとても少ないです。音楽家ではありませんし、まだ子どもですからね。
 コギト
コギト創作するために参考にできる音楽が体に入っていません。
こういったわけで創作の授業の前には特に創作する例となる曲をなるべくたくさん聴かせたり、演奏してみたりして、参考にできる必要があります。
 新米先生
新米先生教科書に載ってる曲だけじゃなくていろいろ聴かせるのが良さそうね…
創作をする前に参考曲を聴かせたりすると、「この後創作やらなきゃいけないから」と結構真剣に聴いてくれ、良い鑑賞の機会になりますよ。
②創作の時間をたっぷりとる
 ブラームス
ブラームスワシが交響曲を作るときに費やした期間はどのくらいか知ってるかね?
ブラームスは交響曲1番を作るのになんと21年の期間がかかったというのは有名な話です。
敬愛するベートーヴェンに負けない交響曲を、と力が入ってなかなか完成しなかったみたいですが、曲を作るのはかなり生みの苦しみがあるもの。
 コギト
コギト私自身もピアノソナタや合唱曲を自作したことがありますが結構苦しみました。(そのころは手書きで書いていました)

この曲の最初の方はスッとアイデアが降りてきて快調に作り始めたのですが、途中の部分でかなり行き詰まって、何日にもわたって1音も書けない、ということもありました。
音楽を作ることに一つの正解はないので、「これかな?」「こっちもいいけど」「あ、こっち治すと、こっちがダメじゃん」という試行錯誤を何度もすることになります。
 新米先生
新米先生授業では限られた時間しかないけど、創作の時間はなるべくたくさんとってあげるといいんだね…
③創作する範囲を絞る
 コギト
コギトいきなり曲を無の状態から作るのは大人でも難しいですよね!
創作の初心者に対して教える小学校の創作の授業では、なんの制限もなく創作を始めさせると失敗してしまいます。それこそ無茶振りですし、自由すぎると逆に何をやっていいのかわからなくなります。
音楽も創作も、本来自由にやるべきだから。みんな、自由につくって!
こういうのは無理ゲー、ってことですね。
逆に思いきって範囲を絞った課題設定をしてあげるのが良いです。
- 1小節だけ
- 旋律のリズムだけ変える
- 和音とリズムは決まっていて後はメロディラインだけ
作曲の作業はとにかく曲が完成するまでのハードルが多く「和音」「音階」「リズム」「音色」などについてある程度学習していないと最初から作るのは無理です。
その上さらに作った曲を「楽譜に書いたり」「演奏したり」しないと完成されたものを確かめることができないので、絵を描くことと違って創作途中の段階では完成形が見えにくいという難点もあります。
 コギト
コギト本当に形になるまでのハードルが高い、高すぎるのが音楽づくり、作曲、創作です。
 新米先生
新米先生ただ「創作しなさい」でできると思っちゃダメだね…
課題に対して初めて臨む子たちが無理なくできる創作の課題を設定しましょう。

この課題では以下のポイントで創作のハードルを下げています。
- 4小節のフレーズのうち、2、3小節目だけの創作
- 創作の段階ではマス目を埋めるだけ、楽譜は書かない
創作(旋律づくり)のハードルを下げる工夫をしよう

創作の授業は先生にとってだけでなく、生徒にとってもハードルが高いもの。
- 見本を多く示す
- 時間をたっぷりとる
- 創作する範囲を絞る
このような工夫をすることで無理なく創作の授業を進めることができます。ぜひやってみてください。
 コギト
コギト以下にコギトが作った創作授業がダウンロードできます!
音楽の授業準備が大変とお困りの先生へ
教材準備の時間を3分の1にして定時退勤しながらも生徒が前のめりになるおもしろい授業をする方法
わかりやすく簡単に創作の授業を指導できる解説&教材のセットを販売中。
- 創作の事前知識(音階や和音など)を完全解説
- 創作の参考曲例が豊富
- ワークシートで簡単に創作が可能
このブログ記事のポイントを押さえた教材セットになっています。
 コギト
コギト創作の授業の教材準備って結構面倒ですよね…
以下のリンクから教員歴18年のベテラン音楽教員が10時間以上をかけて作り込んだ授業用教材が1クリックで手に入ります。
この教材は有料ですが、無料でネットに落ちている指導案やワークシートとはまったく別物。超作り込んだ教材です。教材は随時アップデートも行っているので、教科書が変わって古くなってしまうこともありません。
↓気になった方は教材をチェックです!
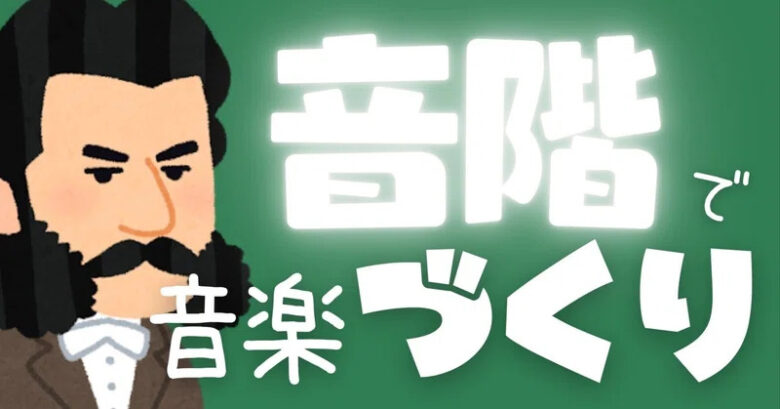



今回は以上です!






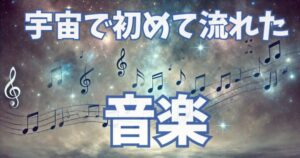


っていつできたの?【音楽授業で使える小ネタ】-300x158.jpg)



コメント